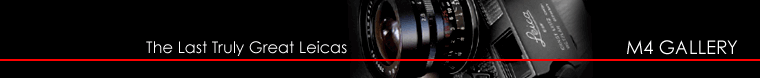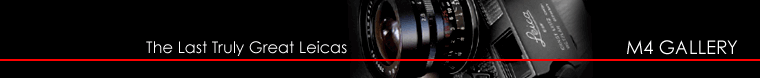| Summicronレンズでの放射能について(1)kaz2002/09/05
(Thu) 17:17 |
 |
ライツは高い反射定数を得るために初期(1950-1951、シリアルでは92万台-100万)のSummicron50/2(製造年がオーバーラップしているので、一部のSummitar50/2も)にはトリウム(原子力材料にもなる)ガラスを採用しました。放射線の対策をしないと、すぐ後ろにあるフィルムは当然カブリを生じるので、ライツは放射能ガラスの背面のレンズ材料に放射能を吸収するフリントガラス(所謂鉛ガラスで、TVのブラウン管からの放射線の放出予防にも使われている)を使うという英国特許を取得して対処したとのことです。(着想と、丁度良いガラスがあったのが面白いですね、しかしISO400では洩れるとも言われています)
ではどのくらいの放射能が出ているかと、アメリカで数本のレンズを測定した結果ではトリウムガラスレンズからの放射線放出量は[1.5ミリレントゲン(mrem)/時]と測定されたそうで、この値は36mrem/日であり、放射線業務従事者の限度13.7mrem/日と比べても大きく、一般人に適用される許容量0.274mrem/1日にはとてつもなく大きな値です。(医療業務従事者の限度は、1950年約100mSv/年[0.274mSv/日=27.4mrem/日]から1990約10mSv/年=2.74mrem/日と推移。1Sv=100rem)・・・・(2)に続く
|
| Summicronレンズでの放射能について(2)kaz2002/09/05
(Thu) 17:19 |
| |
ライツ自身も当初からこのことには気が付いていて、従業員のためにこのガラスの製造工程には特別の注意をし、隔離したそうです。1952年の終わり頃にトリウム無しで同等の光学特性のLaK9(酸化ランタン・光学ガラスの石灰の代替を使って)を供給できるようになり、問題は解決したそうです。
悪いことにトリウムガラスでは、放射性物質の崩壊によって生じた核種(娘核)があるので、ある均衡に達するまでは放射性は増加するために、半減期という概念での放射能の減少は期待できないようなので、50年経過したから大丈夫だろうと安易に考えてはいけないようです。
他のレンズでも放射能が出ていることも分かっていて、その中にはZuikoやTakumarの名前もあります。
アメリカでは相当問題になったようなので、古いレンズは全て調べた方が良いようですが、測定装置(ガイガーカウンター)はそう簡単には貸してもらえないでしょうね。私も今回の調査からSummic50/2用に鉛ケースの準備を考えています。
放射線業界人でも光学レンズ業界人でも無いので、用語などに間違いがありましたら、ご指摘ください。
|
| 放射能レンズの続き・・(3)kaz2002/09/10
(Tue) 23:01 |
| |
放射能が沢山出ている要注意レンズは判明しました、トリウムガラス使用のKodak
Aero-Ektar、1960年半ばのAsahi Super-Takumar50/1.4・35/2、Canon Pellix・50/0.95や35/2FD(Canonからの回答文があり、高屈折率と歪みのためにトリウムが使われたが、放射能の危険は少ないとあります)、Zuiko55/1.2などが特定されています。
Summicron50/2についてはLHSAの文章では1953年まで(シリアル#は不明)同じガラスが使われたとあります。しかし、前述のようにLeitzが初期に対処して使用を止めたのに対して、日本のメーカーではその後に明るいレンズ用として高い屈折率のトリウムガラスを使い出したところに問題がありそうです。
この経過を調べた結果、ほとんどの放射能のあるトリウムレンズが黄変しているので、レンズが黄色くなければトリウムガラスではないようです。 |